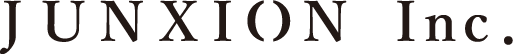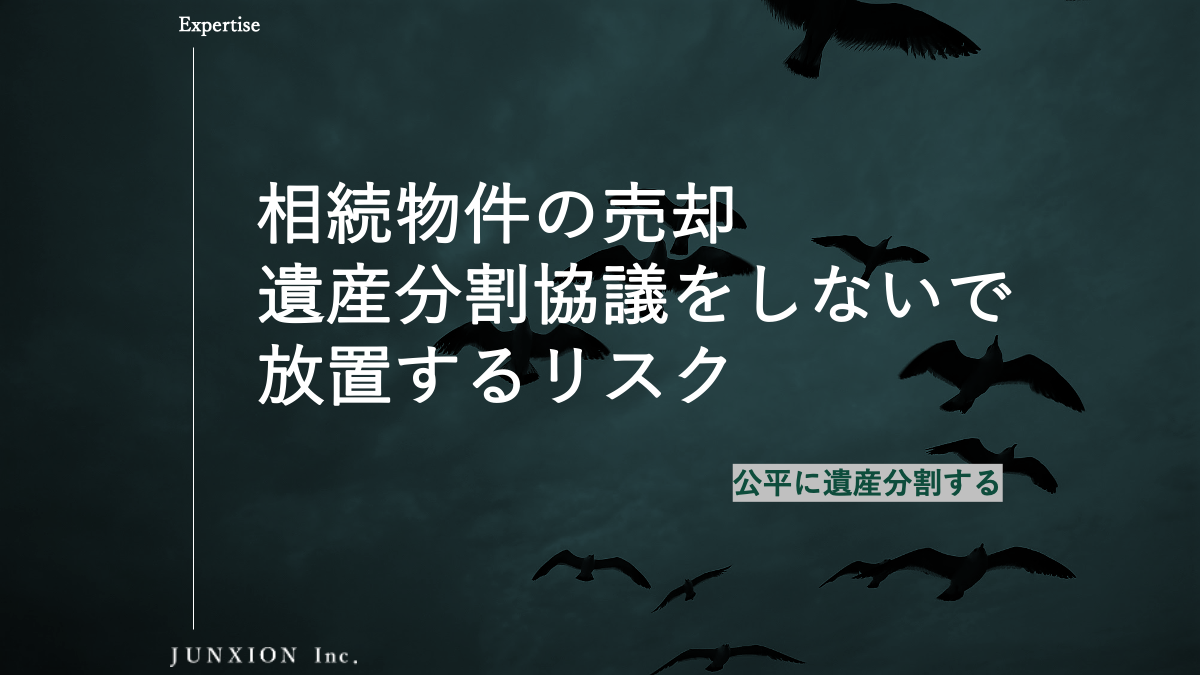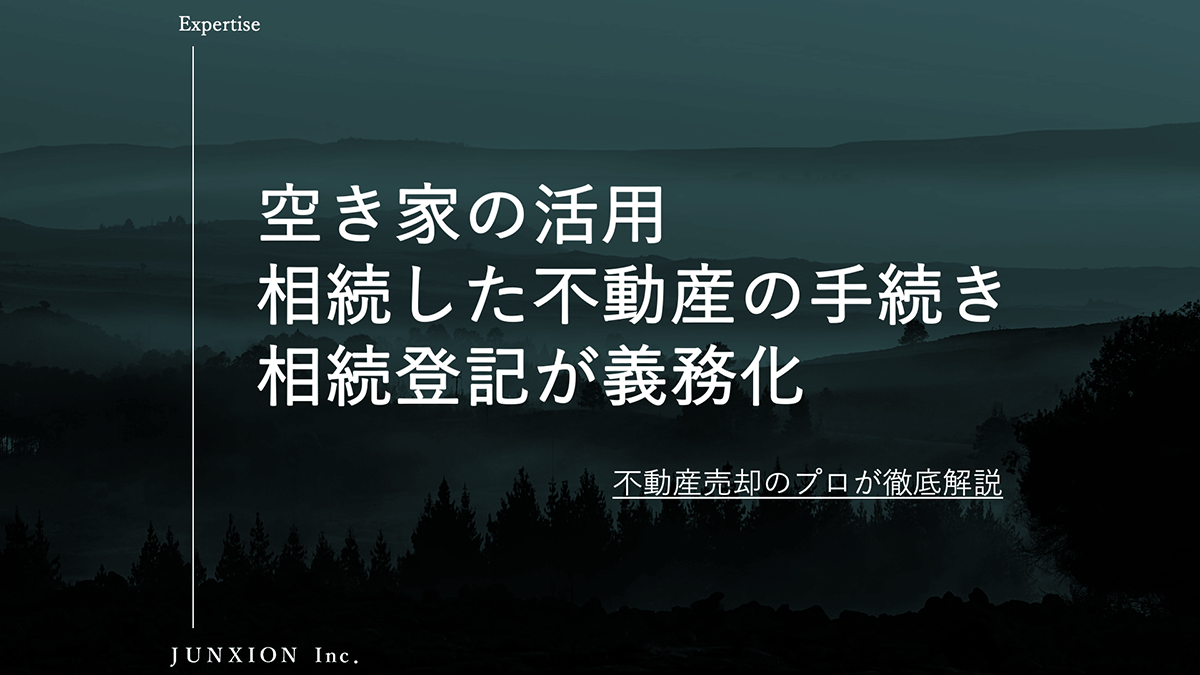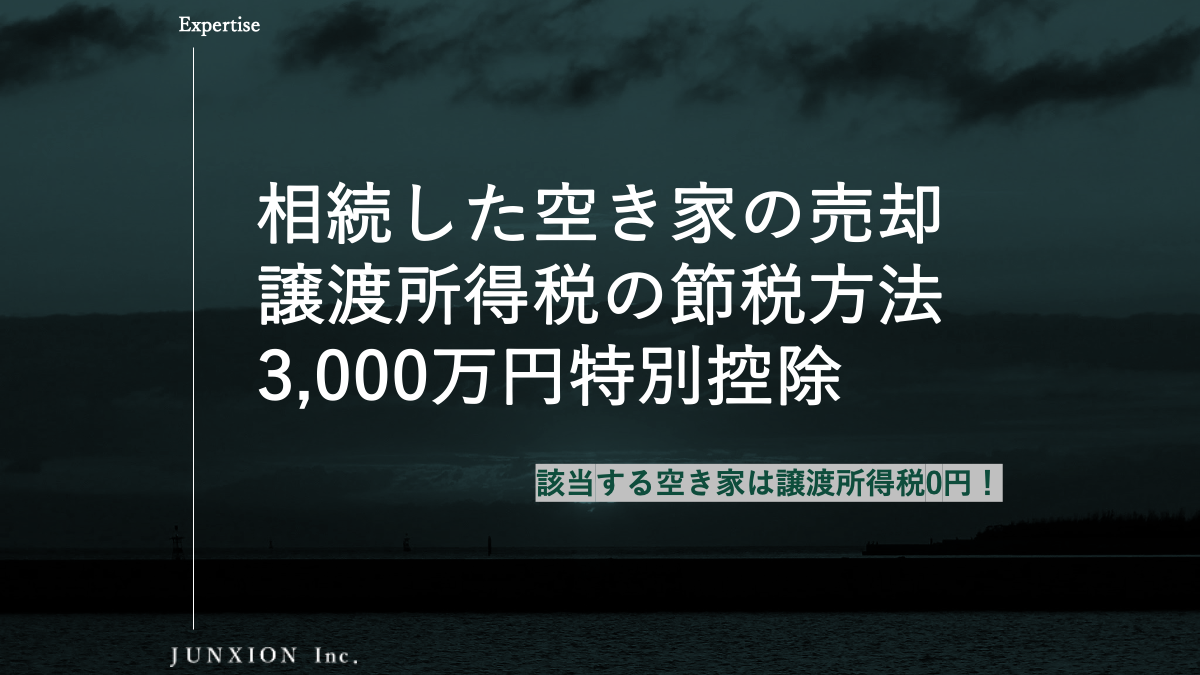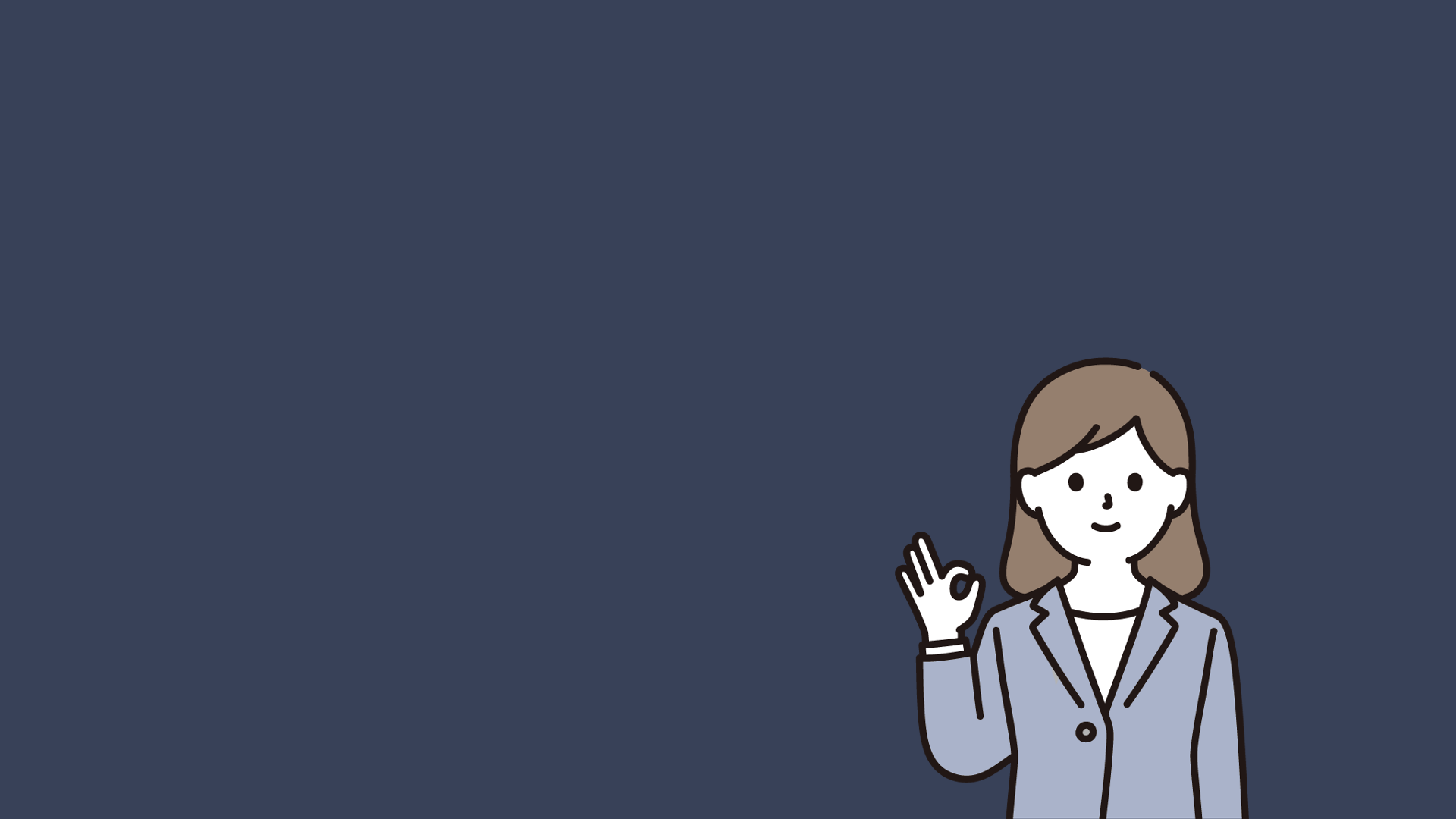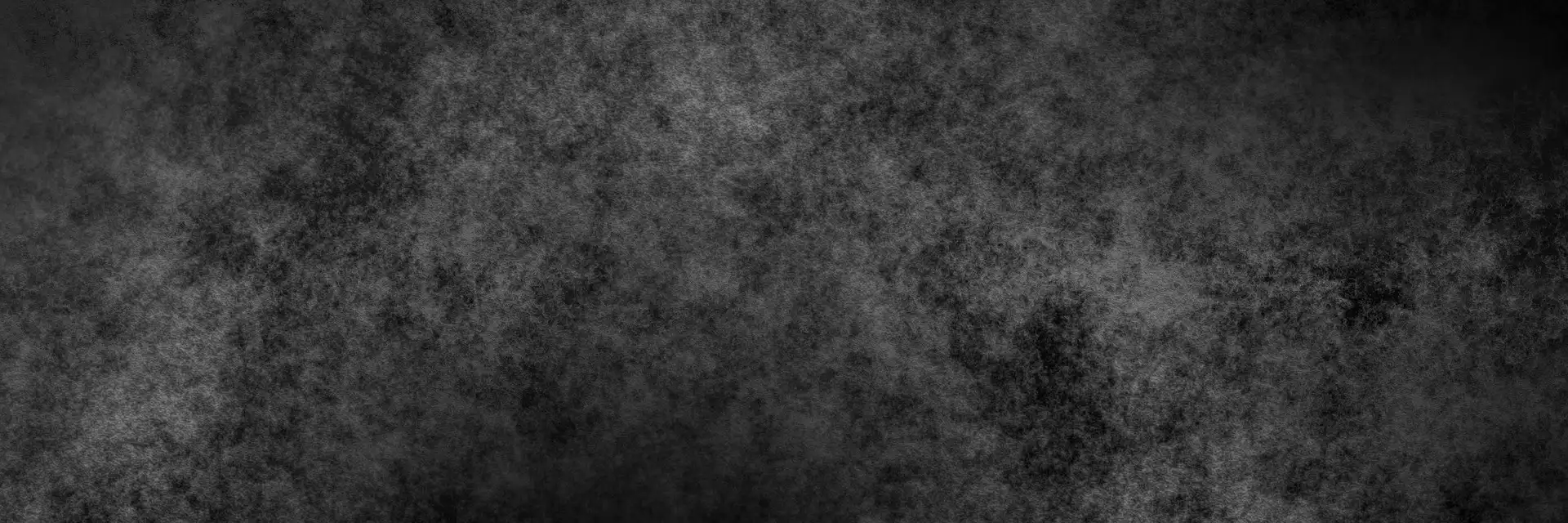相続物件の遺産分割協議をしないリスク
遺産分割協議をしていない相続物件はトラブルのもとです。
・不測の事故が起きても賠償が受けられない
・将来的に相続人が増える可能性がある
・相続物件を自由に売却することができない
・他の相続人が、自分の持分(法定相続分)だけ登記してしまう

遺産分割の法律が改正
令和5年4月1日より前は、遺産分割を行う期間に関する定めは特にありませんでした。
そのため、遺産分割がされずに被相続人名義のまま遺産に属する土地が放置され、誰が土地の所有者なのか登記簿を見ても分からない、という弊害が発生していました。
被相続人の死去後、相続登記をしないまま相続人である子ども、孫が次々に死去し、それに伴い相続も次々と開始されてしまう「数次相続」が起きると、共有者が数十人になり遺産分割協議は事実上不可能となります。
そこで、このような所有者不明土地問題を解消するために法律が改正されることとなり、令和5年4月1日以降は、具体的相続分の割合による遺産分割を求めるためには、相続開始の時から10年を経過する前に家庭裁判所に遺産分割の請求をすることが必要とされることになりました(民法第904条の3)。
従って、相続開始の時から10年経過後に家庭裁判所に遺産分割の請求が申し立てられた場合、裁判所は、具体的相続分に従って遺産分割を行うことができず、法定相続分に従って遺産分割を行うことしかできません。
なお、この具体的相続分による遺産分割を求めるための期間制限に関する規制は、令和5年4月1日より前に発生した相続にも適用されます。
令和5年4月1日より前に相続が発生している事案については、「相続開始から10年経過時」または「令和5年4月1日から5年経過時」のいずれか遅いときまでに、相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたときに限って、具体的相続分に従った遺産分割が可能となります。
具体的相続分とは?
具体的相続分とは、特別受益や寄与分といった事情が存在するケースにおいて、相続人の不公平を是正することを目的とする修正が行われた後に算出される相続分のことです。
特別受益や寄与分が認められるケースでは、相続人間の公平を実現するため、法定相続分とは異なる相続分で遺産が分割されることになります。
①特別受益とは?
相続人の中に、被相続人から遺贈や多額の生前贈与を受けた人がいる場合、その受けた利益のことを「特別受益」といいます。
特別受益が認められる場合、利益を受けた相続人は遺産の前渡しを受けたものと評価されますので、遺産分割に当たってはその人の相続分を減らして具体的相続分が算出されることになります。
存命中に自分の財産を他人に与えることであるが、通常は、相続の前倒しとしておこなう贈与を生前贈与という。
生前贈与をおこなったときには、贈与を受けた者に対して贈与税が課せられる(毎年110万円までは非課税)。
一方、相続した場合に課せられる相続税は、贈与税よりも税率が低い。
そこで、存命中に被相続予定者等に対して財産を分与する必要に応えるために、一定の要件を満たす贈与財産について、相続時にその贈与財産も相続財産と同様に取り扱う制度「相続時精算課税制度」が創設された(2003年)。
また、直系尊属からの住宅取得等資金の贈与等については一定額まで贈与税が非課税となる。
②寄与分とは?
相続人の中に被相続人の財産の維持または増加に貢献した人がいる場合、遺産分割に当たっては、その人の貢献の度合い(寄与分という)に応じてその人の相続分を増やして具体的相続分が算出されることになります。
相続物件を遺産分割協議しない不利益
特別受益や寄与分が認められる場合にこれらを考慮して具体的相続分に従って遺産分割を行う場合と、これらを考慮せずに法定相続分に従って遺産分割を行う場合とでは、各相続人が遺産分割の結果得られる金額が大きく異なることがお分かりいただけたかと思います。
遺産分割の一部権利に期間制限が設けられたため、特別受益や寄与分が認められるケースにおいて、遺産分割に当たって自らに有利な立場を維持したい相続人は、対立する相続人との間で任意の話合いがまとまらない場合、具体的相続分に従った遺産分割を実現するために、相続開始の時から10年を経過する前に家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることが必要となります。
不動産相続登記の義務化
2024年4月に相続登記は義務化されました。
令和6年4月1日以降、相続や遺贈によって不動産を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられています。
正当な理由がないのに相続登記を怠ったときは10万円以下の過料に処することとされていますので、この点も併せてご確認ください。
また、相続登記による名義変更をしなければ、相続した不動産は売却できません。不動産を相続したら、まずはなるべく早い段階で相続登記を済ませておきましょう。
相続物件にかかる税金について
相続税は相続資産3,600万円以下なら非課税
相続税は、相続資産の総額が基礎控除額を超える方が課税対象です。
令和6年1月1日現在、基礎控除額は【3,000万円+600万円×法定相続人の人数】です。
例えば、相続人が1人なら3,600万円、相続人が3人なら4,800万円までの相続資産に相続税はかかりません。
※相続不動産の資産評価額は【家屋=固定資産税の評価額/土地=路線価方式もしくは倍率方式】より。
相続する資産の合計額が、相続税の基礎控除額を超えて納税が必要な場合、相続税の申告および納税は【被相続人の死亡を知った日から10ヶ月以内に相続人がおこなう】ことが原則です。
例えば、1月10日に被相続人が死亡した場合には11月10日が相続人が申告および納税する期限となります。
相続税を納税後3年以内に売却で節税
相続した資産が基礎控除額を超えて相続税を支払った後に、相続不動産を売却(相続税申告期限の翌日から3年以内に相続不動産を売却)して譲渡所得が発生した場合に限り、相続税の一定額を取得費に加算できる「相続税の所得加算額の特例」が認められています。
取得費に相続税の一部を加算することで譲渡益を抑えられるため、譲渡所得税を節税できます。
相続した不動産の売却には税金に関する特例があります。相続したら早めに売却した方が得をするケースも多いため、相続に詳しい不動産会社へ相談するのがオススメします。
相続物件でも売却益は申告
相続した不動産でも、売却して譲渡所得(売却益)があれば課税対象です。
売却代金−(取得費(※減価償却要)+経費)
取得費は被相続人が購入した当時の不動産売買契約書などをもとに、減価償却した金額から算出します。
売買契約書などを無くしてしまい取得費が分からない場合は、相続した不動産を売却したときの譲渡金額5%相当額を取得費と計算できます。
相続した空き家を売却したときの特例
相続した空き家を売却するときには、譲渡所得税を節税する特例があります。
相続物件を売却して利益があれば譲渡所得税が課税されますが、一定の要件を満たす相続空き家の売却なら、譲渡所得課税の特例による特別控除額を譲渡所得から差し引くことが可能です。
平成28年度税制改正で創設された「相続等により取得した空き家を譲渡した場合の3000万円特別控除」が改正され、令和6年1月1日以後の売却について適用対象範囲が拡大されました。
空き家の相続物件を売却したときにかかる税金の節税効果が大きいこのタイミングで売却するのがおすすめです。
相続物件は専門家に相談する
相続物件は遺産分割協議や相続登記など、手続きが多い特徴があります。
遺産分割協議は、タイミングを逃してしまうと「なぜ今さら?」と他の相続人との交渉も難しくなってしまうことも多いでしょう。
相続人が多いほど問題が複雑になる相続物件の遺産分割協議は、なるべく早いうちに手続きすることをオススメします。
大きなトラブルを防ぐためにも、不動産の相続が分かったら司法書士などの専門家へ相談すると良いでしょう。
当社では信頼できる司法書士を無料で紹介しておりますので、お気軽にご相談下さい。
ここまで「相続物件を遺産分割協議しないで放置するリスク」を解説しました。
相続物件がトラブルを引き起こすリスクを回避する方法は①遺産分割協議や相続登記を済ませる②使用しない相続物件は売却することです。
相続物件の売却なら『売却専門の不動産会社ジャンクション』にご相談ください。
不動産売却相談×年間実績1,000件以上
不動産売却のプロとして「あたりまえの仕事」を心がけ、数多くオーナーのご期待にお答えしてきた私たちなら力になれるはずです。
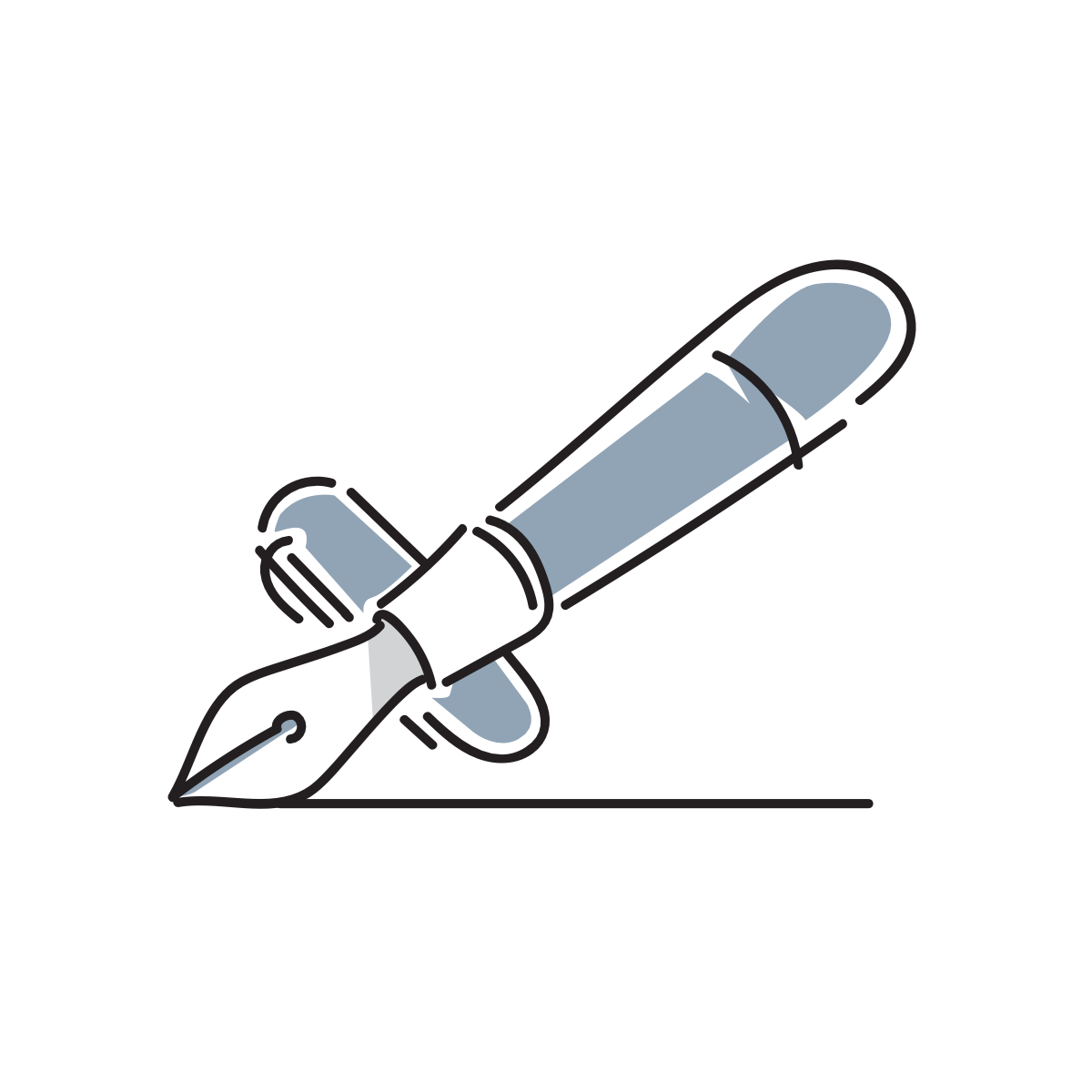
\不動産売却のプロがトータルサポート/
無料相談!売却成功へアドバイス!
いますぐ電話で相談する
0120-750-180
しつこい営業はございません。
不動産のお悩みは人それぞれ。まずは相談を
営業時間/10:00〜18:00 火・水曜定休